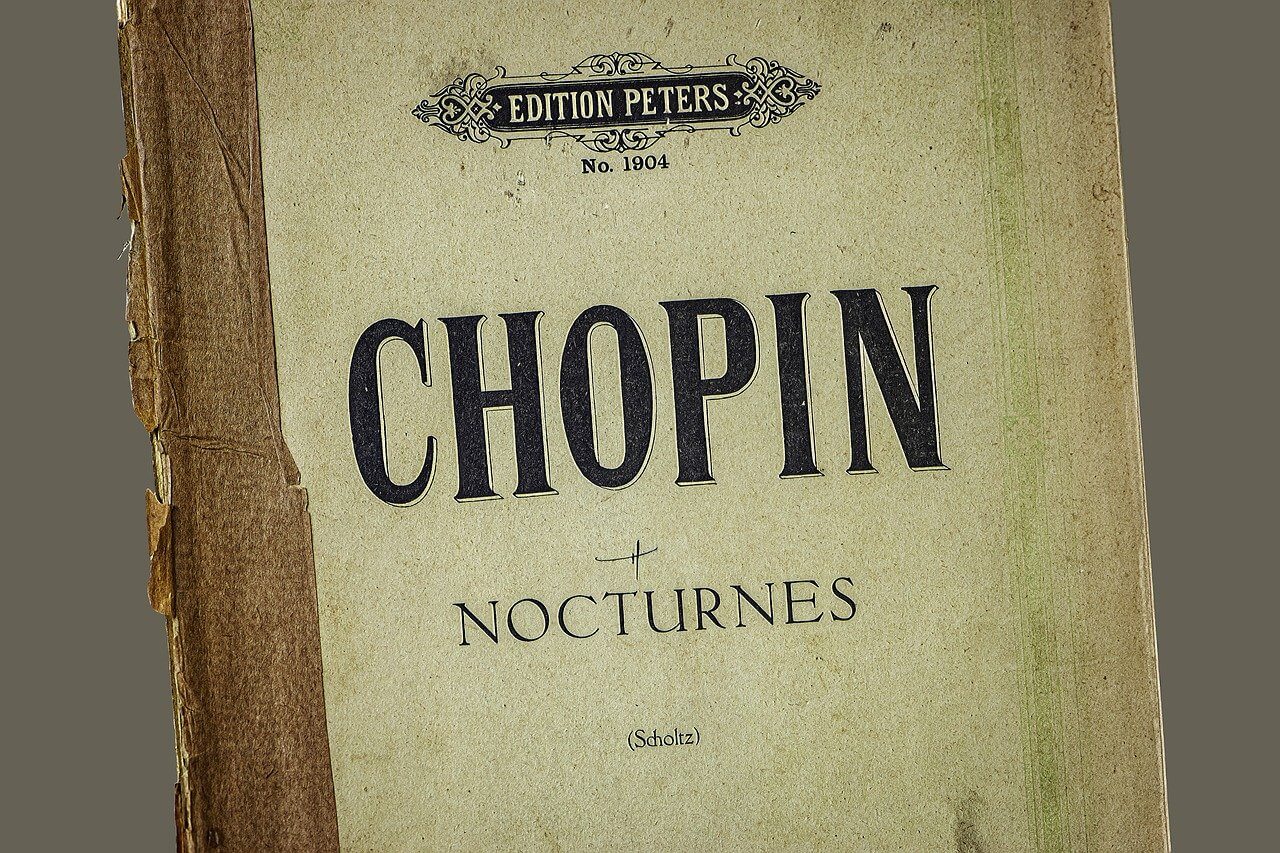〈連想第87回〉
ショパンの作品をジャンルごとに連続してとりあげていますが、今回はノクターンを取り上げます。
ノクターンは、一般的なショパンのイメージに最も近い、優雅で優しい曲調が特徴で、夜想曲という名のとおり夜寝る前などにくつろぎ瞑想することなどをイメージしたものです。
ピアノ独奏のノクターンは、アイルランドの「ジョン・フィールド」が創造したもので、3部形式からなり、ゆっくりとした伴奏にメロディーを乗せるというシンプルな構成のものです。
ショパンはフィールドのことを終生尊敬しており、初期の頃はその影響が顕著でした。
ポーランドを離れて間もない駆け出しの頃には、フィールドと並んで評価されたことをとても喜び、嬉しかった気持ちを誇らしげに故郷への手紙に「あのフィールドと並び評価されたんだ!」という感じで綴っています。
その時すでに2つのピアノ協奏曲や練習曲作品10などを作曲していたこと考えると、当時の評価とその後の評価の大幅な開きを感じて面白いです。
ショパンにとって偉大な存在だったのは同期とも言うべき存在のリストやシューマンではなく、フィールドやモシェレスでした。
しかし今日、リストやシューマンは多くの人の知るところですが、フィールドやモシェレスはあまり演奏される機会はありません。
これは、全ての音楽のジャンルに古今東西共通する現象だと強く感じます。
それは、多くの人に知られる存在というのは突出した一握りの人達だけで、その影には無数の実力者、影響力を持つ人、才能のある人、パイオニアの存在があるということです。
それらの人の存在によって、その分野の奥深さ、底の深さが築かれ、成り立っているのだと、どんな音楽を聴いていても思います。
フィールドの音楽は演奏される機会はほとんどありませんが、ショパンに影響を与え、ノクターンを創始しただけあって、美しく、非常に質の高いものでした。
そんなフィールドから影響を受けたショパンのノクターンは、マズルカと同様、全ての年代において作曲されているので、時代の変遷がわかりやすく、時を経るに連れて重みや深みが増していきます。
初期の頃のうっとり美しい曲調から、晩年近くの深く心に響くものまで、内省的なマズルカとはまた違ったショパンの一面を感じることができます。
言うなれば、マズルカは自分のために書いたものだったのに対して、ノクターンは聴き手を意識して書いたものだったと言えるかもしれません。
今回はそんなノクターンから5選します。
1 第2番 変ホ長調 作品9-2(1831)
誰もが知るショパンの代表曲。
別れの曲と並んで、もしくはそれ以上にショパンの代名詞的曲で、聴いたことがない人はいないのではないでしょうか。
かつてフィギュアスケートの浅田真央選手が、この曲で圧巻の演技をしたことでも有名です。
なぜこの曲がここまで有名・定番になったのか。決定的な何かを見出すことはできませんでしたが、親しみやすいメロディーが多くの人に愛されてきた、その思いが受け継がれてきた、ということなのでしょう。
ショパン自身も「この曲のメロディーが最も美しい」という趣旨の発言をしています。
演奏は、ショパンの演奏を多く残している、あの「セルゲイ・ラフマニノフ」です。
作曲家としてだけでなくピアニストとしても活躍した、ロシア帝国出身の巨人です。
2 第5番 嬰ヘ長調 作品15-2(1831)
9-2とほぼ同時期に作曲された(出版は2年後)曲で、演奏会などで取り上げられることも多い著名な曲。
ノクターンらしい甘美でメロディアスな曲調の中に、作曲技法における様々な創意工夫がなされています。
演奏は、ロシア帝国(現ウクライナ)出身で、ポーランドの初代首相兼外務大臣も務めた異色のピアニスト、「イグナツィ・パデレフスキ」です。
3 第8番 変ニ長調 作品27-2(1835)
ノクターンの中でもとりわけ傑作の呼び声高く、演奏機会も多い名曲。
半音階進行が多用されており、それがすごく近現代的な響きと空間を漂うような幻想的な雰囲気を醸し出しています。
まさに、ノクターン=夜想曲のイメージにぴったりな真骨頂的な曲と言えると思います。
演奏は、コルトーやブーランジェらレジェンドに師事した不世出の天才ピアニスト、ルーマニアの「ディヌ・リパッティ」です。
4 第18番 ホ長調 作品62-2(1845)
生前最後に書かれたノクターン。
最後のノクターンに相応しいと言っても過言ではないほど洗練され、美しく深みのある曲調となっています。
演奏は、1985年ショパンコンクールで優勝したあの「スタニスラフ・ブーニン」の祖父で、シベリアに追放された経験も持つロシア帝国(現ウクライナ)出身の「ゲンリヒ・ネイガウス」です。
5 第20番 嬰ハ短調 遺作(1930)
ショパンの作曲における第一次黄金期とも言える20歳前後に書かれた曲。
映画「戦場のピアニスト」で使用されたことで一躍著名な曲となりました。
ショパンの生前は出版されずタイトルもついていませんでしたが、死後、ショパンの姉のルドヴィカが「ノクターン風レント」とタイトルをつけてためノクターンとして位置づけられて、遺作として出版されました。
しかし内容は、同時期に作られたピアノ協奏曲第2番のスケッチ的要素が強く、複数のフレーズがそのまま使われています。
この曲を聴くと、神曲「ピアノ協奏曲第2番」を聴きたくなります。
演奏は、飾り気なくストレートで力強い表現が胸を打つ、2005年ショパンコンクールで「ポーランド批評家賞」を受賞した「辻井伸行」さんです。
今回は、ショパンの優雅なイメージそのままのノクターン=夜想曲を取り上げました。
さて、これまでドビュッシー〈ショパン関連曲〉で取り上げた曲の大元のショパンの曲を取り上げてきましたが、次回は、ショパン晩年の重要な名曲、「舟歌」「子守歌」「チェロソナタ」の3曲をあわせて取り上げてこのシリーズを終わりにしたいと思います。